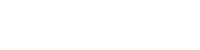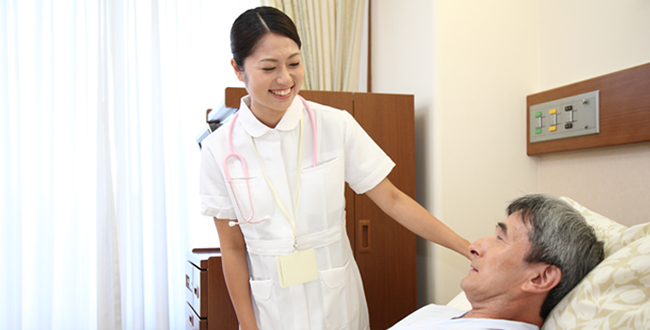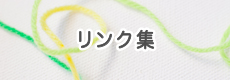日本には、古くから看取りを示す「取り見る」という単語があり、例えば北里大学名誉教授の新村拓さんは『万葉集』に出てくる、山上憶良の「家にいて母が取り見ば慰むる・・」等の短歌を示してその背景を考察しています。また律令制下では80歳以上の老人には、その子孫や近親等の血縁者、それらがいない場合は地縁者の誰かが看護人(待丁)となることが定められていて、看護人となった者の税には減免措置等が行われたと言うことです。「相互の情誼に訴え、相互扶助を持って公的扶助を肩代わりさせた」と新村さんは述べています(新村拓, 1991: 111-112)。
日本における終末期の看取りは、往生思想による臨終所作として宗教的な領域で長く伝えられてきたが、明治期を経て、看取りは家族の問題となり、やがて国策として女子教育の「家政」の中で位置づけられるものとなっていきます。看取りの技術や知識は家事を担う主婦が身につけるべきものであり、家政学の教科書等には看取りの作法だけではなく、遺体の初歩的な処理の仕方まで掲載されていました。昭和中期までは一般家庭における在宅死は当たり前のことであり、嫁や妻が専従で看取りを行い、そのための技術や知識は家や地域社会に継承されていたのです。しかし、死の医療化とともに、医療機関での死亡率が高まり、死を迎える文化は家や地域社会から廃れてしまいました。
医療人類学者である御茶ノ水女子大学名誉教授波平恵美子さんは国内各地の村落調査を実施したさい、あらかじめ設定したテーマとは別に多くの病気や死に関する語りを収集することになったそうです。各地で継承されていた看取りの作法や価値観について興味深い事例の報告を行っています。それらから浮かび上がるものは「多様な死の状況であり、それぞれの死に際して残された人々の多様な反応である」と記しています。(波平,2004:86) 群馬県にある緩和ケア診療所いっぽの医師萬田緑平さんは、これまで支援してきた在宅での看取りに関して「穏やかな最期を迎えることができたご家族には、唯一にして最代の共通点があります。それは、「死を受け入れていた」ということです」 と言っています。(萬田,2013:142)
かつて日本にあった看取りの文化は、今後大介護を時代を迎えるにあたって改めて再生しなければならない文化ではないでしようか。しかしこの新たな「看取り文化」は医療資源が乏しく、システムとしての介護制度が確立していなかった以前の看取り文化とは異なるものです。医療と介護の連携が叫ばれている現在、地域包括ケアシステムという受け皿の中で家族介護者が身につけていく新たな看取り文化の再生が期待されているのです。
参考図書
● 新村拓『老いと看取りの社会史』法政大学出版局 1991
● 波平恵美子『日本人の死のかたち 伝統儀礼から靖国まで』朝日新聞社 2004
● 萬田緑平『穏やかな死に医療はいらない』朝日新聞出版 2013
⇒ 緩和ケア診療所いっぽ http://www.ippo-kai.com/index.html
● 林美枝子 「在宅死に関する新たな家族介護者像の模索と看取り文化の再生の可能性について」 札幌国際大学紀要,45, 77-85.