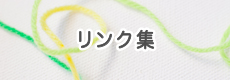カルテの余白 ~ある女性患者の最期~
日本医療大学 元学長 傳野隆一
道南の港町にある病院に外科医長として勤務していた時の話です。その港町は、その昔、北前船が入港し、繁栄を極めましたが、今では歴史的建造物や貴重な文化財となって保存されている歴史のある街です。 ある時、高齢の女性が乳癌を患って受診されました。その方は、受診する機会を逸したと思われ、かなり進行した状態でした。大学から先輩医師の応援をうけ、手術は無事に終えることができました。術後経過も順調で時々外来に通院されていました。しかし、残念なことに、その後、局所再発に加え、骨・肺にも転移巣が見つかりました。外来治療が困難になった時点で入院していただき、疼痛コントロールのため麻薬を処方していました。入院されてからは、ほとんどの時間をベッドの上で過ごされていましたが、笑顔を絶やさず、笑うと残り少ない歯が顔をのぞかせる笑顔の素敵な方でした。ところが医局の都合で私自身が札幌へ移動しなければならなくなりました。当時としてはホスピス病棟がある稀な病院でした。するとそこにその患者さんも一緒に移ってきてしまったのです。札幌に娘さんが住んでいるということもその理由のひとつでしたが、私自身とても驚きました。住み慣れた所を離れなければならなかったのは、さぞ辛いものだったであろうと察するに思いあまりますが、ご本人は最後場を覚悟されていたのでしょう。今の医療制度では、急性期の治療は治療可能な病院で行い、その後は、患者さんの近くの病院で経過を診ることになっています。誠に理にかなった病院の役割・機能分担であります。しかし、患者さんとの結びつきが強いと、中には最後まで看取るケースもあります。勿論、この患者さんも最後まで看させていただいたのは言うまでもありません。彼女が息を引き取る時に、にっこりほほ笑んでくださったように見えたのは、自分の思い込みだけではないと思っています。最近は緩和ケア病棟を設けてある病院が増え、終末期の状態にある患者さんを看ています。そこに勤務している緩和ケア医が、実は元外科医であることが多いのです。それは、手術を通して患者さんと医師の結びつきが強いため、終末期を看取ることが多いことによるものと思われます。 今、日本学術会議では、ホームドクターの在り方について検討されているようです。ぜひ国民が安心して死を迎えられるような制度を作り上げていただきたいものと願っております。(リビング・ウイル北海道 No.79 2008年6月30日より転記)
追記:林教授が『看取りと介護の語り場』を企画されました。さらに,HPを立ち上げることによって多くの皆様方が集い,語らい,そして新しい看取り文化が再構築されることを願っています。